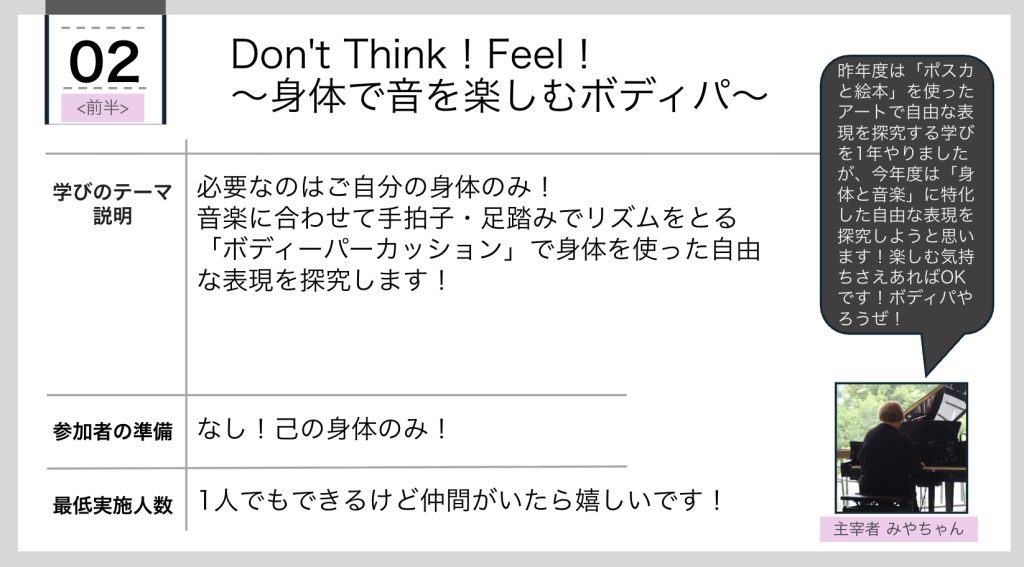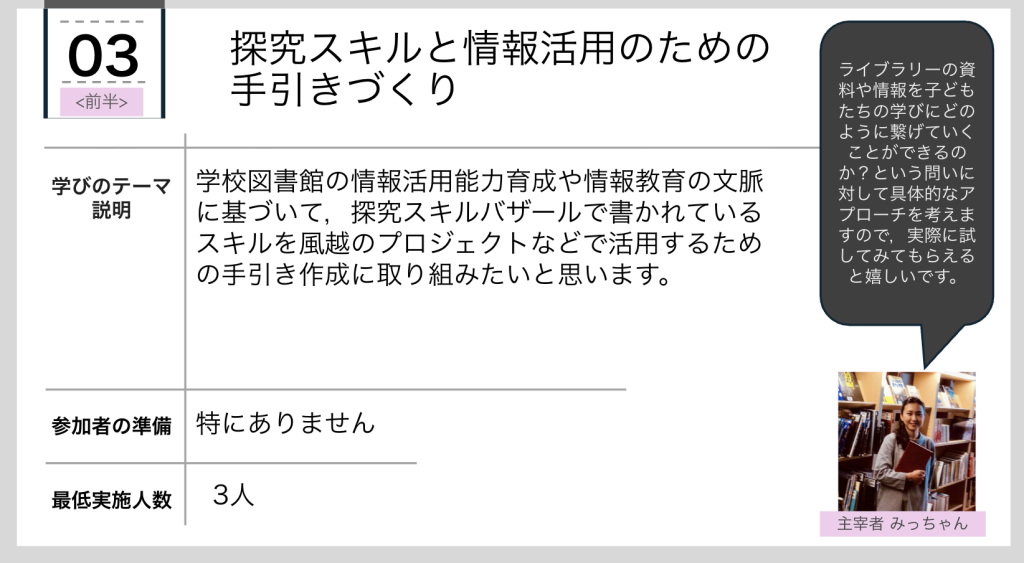大人の学びと働き

2025年9月30日
研修ブランチを引き継ぐ
7月のある日、管理職との面談でゴリさん(岩瀬)とたいち(井上)から「研修ブランチの担当、ようへい引き継いでくれるかな?」と投げかけられた。同期のふぅ(林)が研修ブランチの担当(ひとりで!)だったのだけど、ふぅがしばらくお休みに入るので、その引き継ぎを探しているとのことだった。
「研修かー…そんなに余力はないけど、面白そうだとは思っています。やりたい気持ちが半分、やりたくない気持ちが半分、というのが正直な気持ちです。ふぅのお願いなんでやります〜」
と、研修ブランチの仕事を引き受けることにした。とはいえ、研修ブランチの仕事ってどんな仕事?というのが正直な気持ちだった。よくわからないから、ゴリさんに「どんな仕事?」って聞いたし、ゴリさんからもねがいを伝えたいと言われて話を聞いた。
「「風越学園はホームページに書かれているように、スタッフの学びを大切にしている。 他の学校に比べてスタッフ研修の時間がすごく多い。週に1回スイゴゴ(水曜午後の研修の時間)があるし、月に1回一日研修日がある。 大人の学びが学校組織の真ん中にあることがとても大切。風越で、スタッフの学びが積み重なっていくことはこれから公立学校が変わっていくための大切なメッセージになると思うんだよね」
それは本当にそう思う。子どもたちが学び続けることを期待する学校において、学校にいる大人が学び続けることをするというのは最も大切だと思う。楽観的かもしれないけど、それが実現できれば子どもたちは学び続けると思う。でも、「実際にはどうしたらいいの?」って感じだ。
ふぅに聞いて研修ブランチの仕事を一旦整理すると、こんな感じだった。
- 各ブランチに研修の場を開くことをお願いしたり、要望があれば調整したりする。
- ディレクターチームと研修について相談する。
- 研修ブランチ独自で研修の場を開く(今年度のテーマは「コミュニティという視点を深める」)
9月頃、ふぅが「今まで大切にしてきた幼稚園と小学校1・2年生の接続についてアウトプットしたい!」と言うので、9/10(水)のスイゴゴはマルシェ(お題を持ち込み形式)というかたちにした。ありがたいことに4つもお題が集まったので、次のような構成にした。
全体(30分):やめよう会議ーやめるやめようじゃないけどさ by ふっしぁん(藤山)
選択①(60分):かぜのーとを書こう by たつみさん(辰巳)
選択②(60分):お金集めについて考えよう by とのちゃん(外崎)
選択③(60分):伝えたい1・2年生のこと by ふぅ
やめよう会議ではふっしぁんとジョセ(金子)から「風越のいいところって変えられることだよね」「やめることを決めるわけじゃないけど、一旦話してみることで感じることがあると思うんだよね」という投げかけがあった。それぞれ小グループから「変形労働時間制にしよう」「いろいろ変わっていく風越のなかで残っていくもの(ホームやアウトプットデイ)と残らないものの違いって何だろう」「油断すると安定しちゃうから、例えばオフィスの場所をルーレットで決めよう」「やめよう会議は何を目的にしているんだっけ?」「手をふくペーパータオルをやめよう」「余白のあるスイゴゴをしよう」などなど…いろいろな考えがでてきた。
やめよう会議は、凝り固まったからだをほぐすような時間だったと思う。わりといい感じだったなと思っているけど、「これだと単発的か?」とも思ったり、研修が積み重なっていくってどういうことなんだろうーともやもやも募った。
幼稚園と義務教育学校
ふぅが産休・育休に入ったら、研修ブランチは僕1人になってしまう。それはむりむりかたつむり。だから、仲間を募りたいなと思っていた。風越学園は12年間のつながりを大切にしているけど、スタッフ1人で12年を見れるわけではない。さらにいえば、幼稚園と義務教育学校では、それぞれのスタッフが風越に来る前に積み重ねてきた風土や文化も違えば、活動場所も活動内容も違うし、カリキュラムの性格も違う。そういう違いを、協働していくには絶対に幼稚園のスタッフが研修ブランチに必要だなと思っていた。
それで、白羽の矢を立てたのがみなみ(手塚)だった。僕とみなみは同じ世代ということで話しやすかったり、みなみの独特な雰囲気が面白かったり、みなみとだったら一緒にできそうだなと思って声をかけた。声をかけたとき、みなみは「えー」って顔していたかな(笑)。
みなみ:研修は大切だと思うんですけど、研修の方向性がよくわからなくてー…(汗)。
ようへい:そうねー。実践をよくするためには大人の学びはきっと必要だと思うんだよね。そこに向かっていくといいのかなー。
みなみ:それはよくわかります!ちょっと荷が重いですが、やります。
研修ブランチに入ってくれたので、とても感謝している。少し一緒に働くだけでみなみの真面目さがわかる。スイゴゴの時間が幼稚園と義務教育学校の違いを超えてそれぞれのスタッフにとって意味のある時間になったらいいなと切に思う。
大人の働き
あるとき、ふぅが「スイゴゴの出席率が気になっているんだよねー…」とつぶやいていた。どうしても日々の仕事が圧迫していて、心や身体を整える時間は必要だなってすごく感じている。その時間をとろうとしたらスイゴゴになりやすい状況だなとは思う。
そんな状況のなかで、どうしたらスイゴゴの参加度を上げられるだろう。大人の学びが充実することは、子どもの学びにとっても重要である。しかし、大人が日々の実践で忙しければ学びを充実させることは難しい。目の前のことに追われて、じっくり深く考えられないのは当然である。日々忙しいのに「じっくり学びましょう」って言われても僕だったら困っちゃう。
そうやって考えると大人の学びだけじゃなくて大人の働きももう少し考えたい。例えば、子どもの下校時刻を15:00にするとか、水曜日だけじゃなくて金曜日も午前時程にするとか(夏休みは短くなるかもね?)、必ず木曜日の16:00〜17:00はミーティングをいれないとか。何が忙しさの原因になっているかははっきりしないけど、原因が複雑すぎる気がしているから原因を分析するよりいろいろ試したほうがいい気がする。
大人の働きを考えるチームってどこにあるかな?従業員代表かな。法規的なところだけじゃなくて、一日の過ごし方とかカリキュラムや協働、ミーティングの圧迫感とか、そういうところも含めて扱うチームがあってもよさそう。立ち上げようかな。もう少し言えば、そういう大人の働きと、大人の学びを一緒に扱ってもいいと思い始めた。スイゴゴの時間がどんなにいい時間になっても、忙しくて疲れてしまったなら参加したいとは思えない。このことは「学び」が「仕事」に含まれているような学校固有の難しさのような気もする。だからこそ、大人の学びと働きを一緒に考えるチームが必要じゃないかと思い始めている。
大人の学び
大人の学びというとスイゴゴだけではない。大人の学びについて風越で今のところおかれている仕組みは6つあると思う。
- 学びの日
- 探究テーマでおしゃべり。
- けんさん金制度
- 軽井沢風越学園ラーニングセンター
- メンター制度(新入職スタッフのみ)
- スイゴゴ
学びの日。研修日の時間で半日おかれている。子どもたちのカリキュラムでいえば、マイプロジェクトのような時間。有志のスタッフが場を開く。例えば、今年度は「Don’t Think! Feel!〜身体で音を楽しむボディパ〜」のように日々の実践から遠いものもあれば、「探究スキルと情報活用のための手引きづくり」のように日々の実践に直結するようなものもある。ひらかれた場を一人ひとりのスタッフが自分の興味・関心に基づいて選んで、学びを深めていく。これはとっても大切な時間。
探究テーマでおしゃべり。普段働いていると出会わない3人でグループを作り、自分たちの問いについておしゃべりする時間。そこまで余力はないときは雑談になるときもあるけど、それはそれで意味のある時間。
けんさん金制度。一人あたり年3万円を自己研鑽のために自己裁量で使用可能。僕はほとんど書籍に費やしている。とてもありがたい。
軽井沢風越学園ラーニングセンター。学園での実践に根差した教師教育の研究機能。スタッフの教員としての育ちを支援する取り組みを行っている。
メンター制度。新入職のスタッフ一人に対して、すでに入職しているスタッフが一人つく。風越で仕事をし始める中で、いろいろな疑問や困り感に直面することになるので、何でも聞ける相手としてメンターをつけている。不定期におしゃべりをしている。
そして、スイゴゴ。各ブランチやカリキュラムディレクター、研修ブランチで場を設計して研修をする時間。子どものカリキュラムでいえば、テーマプロジェクトのような時間。専門的な知識や技能について「知る・できる」ってときもあれば、カリキュラムや学校の仕組みを「つくる」ってときもある。例えば、過去のかぜのーとを遡ると、ファシリテーターについて学んでいる研修があった。これは「知る・できる」という感じがする。
一方で、今年度やっている「来年度のカリキュラムどうするの?」とか「記録と評価をどうやって12年間つなぐの?」っていうのは「つくる」感じがする。何かを「知りましょう・できるようになりましょう」って感じではない。研修ブランチという立場になったっときに「知る・できる」「つくる」の両方を含んでもいいのかはちょっと悩む。いや、両方を含んでいいんだろうけど、「知る・できる」の時間がスイゴゴの時間ではちょっと少ないのでは?と気になっているかな。
一方で、学びの仕組みとしておかれていない時間でもスタッフは学んでいる。風越では協働の思想が強く、文化として確かに存在しているので、他者と働く中で自分ひとりでは気付けなかったことに気づく時間は多いだろう。研修ブランチ、マネジメントチーム、カリキュラムディレクターから見えない学びはたくさんある。かといって、それだけでは風越として一つのことに向かっているという感じはしない。「つくる」ということを風越が大切にしているなら、それに向かって何かを学んでいくということは必要だとは思っている。
そうは言っても、あまりにも公的な性質を強めると、「やらされ研修」や「受け身の研修」になってしまうわけで、そこが難しい。そういう意味で、前回のマルシェは自分で内容を選べるという点で、公的な性質と私的な性質のバランスをとっていたと思う。
そうやってぐるぐる悩んでいるとき、『風越の「大人の学び」の出発点ってどんな感じだったんだろう?』ってかぜのーとを探ってみると、2020年にたいちが書いたこんな記事が見つかった。
「子どもが一人ひとり違うように、大人も学ぶべきこと、学ぶペースは違います。余白が大事だと分かっていながら、つい欲張って研修を詰め込んでしまったり「みんなで一緒に」という形をとってしまっていました。決められたことを学ぶようになると、学びが手元から離れていく。それは、子どもも大人も同じでした。そこでもう一度、研修全体の進め方を見直すことに。今回始めた大人の学びの時間から、開校後も、子どもたちが学ぶことで、カリキュラムも変わっていくんだろうなぁと想像しています」
おー。こんな感じだったのか。「余白」は大事だってわかっていても、つい欲張って研修を詰め込んじゃう。今まさにそんな感じ。次回9/17(水)のスイゴゴで何をやるか決まってなくて詰め込もうとしている自分がいる。そもそも「余白」って何だろう。このかぜのーとにはこんなことも書いてあった。
「一方で、スタートしてみると、うまくいかないことも出てきました。たとえば、あるスタッフは『徐々に個人の余白の時間がなくなっていくのが気になる。計画にも個人でやりたいことを書く欄があるのに、実際にその週に入ると全員が対象とされる予定に上書きされる感じも楽しくはないかな。4月からのことを思うと、制度として時間割化すると学びが手元から離れていくことが気になる。』と研修記録に書き込んでいました」
どうやら「余白」とは個人の手元感とも関わってきそう。「何もおかない」余白もあれば自分で選べる「余白」もあると思う。だんだん「みんなで一緒に」なると、自分で選べる「余白」がだんだん少なくなってくる。じゃあ「余白のあるスイゴゴ」ってどんな感じなんだろう。大人の学びには学習指導要領や教科書のように体系化されたカリキュラムはない。それに、大人のカリキュラムは学習指導要領のように「やらなきゃいけない」という性格もない。仕事は給与をもらっているから「やらなきゃいけない」ことだけど、実践の質を高めることは学習指導要領ほど「やらなきゃいけない」ことって感じでもない。だからこそ、大人たちが学びたいと思えなければ「やらされ感」がどうしても強くなってしまい、「余白」の少ない感じになっていく。
もやもやしてきたー。そもそも大人の学びは風越のなかでも外でもいろんなところで生まれている。スイゴゴだけが大人の学びではないし、「余白のあるスイゴゴ」や「学校のための積み重なる研修」をそれぞれやろうって感じでは目指している「風越の大人の学び」にはならない気がしている。「受け身の研修じゃなくてスタッフ主体の研修」をしたいわけでもない。
うーん、問いがはっきりしていないんだな。自分に問い続けたい問いはなんだろう。「大人の学びって何だろう」「子どもの学びに伝わる大人の学びって何だろう」「風越学園として大切にする大人の学びって何だろう」「大人が学ぶときってどんなときなんだろう」「大人の学びが停滞するときってどんなときだろう」「大人が学び続ける仕組みと関わりって何だろう?」・・・
・・・「大人が働き続け学び続ける仕組みと関わりって何だろう」と「大人が働き続けて学び続けるって何だろう」かな。
「すっきりしたー」って感じにはならないのだけど、まずは初心の気持ちをここに表明したということで終わろうと思う。研修ブランチ頑張るぞ。