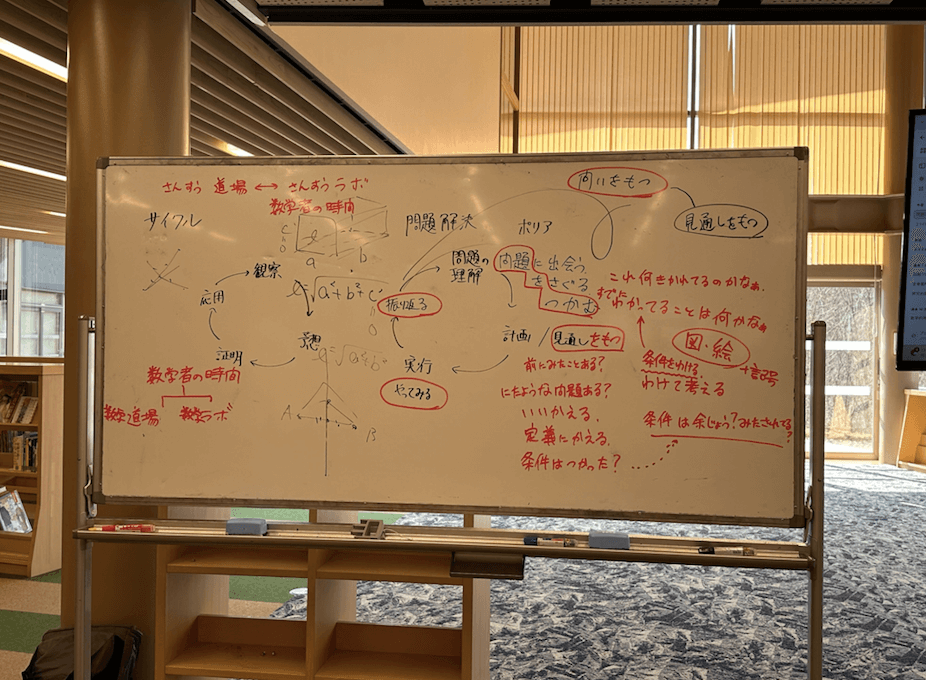土台の学び「地球と人」ってなんなんだろう 〜ぱわー編〜

2025年4月14日
読み手のみなさんは軽井沢風越学園のぱわーと聞くと、何をイメージするのだろうか。”地球と人”と答える人はどれほどいるのだろう。
僕自身と地球と人との距離感はというと、よくわからん。
地球と人を実践している自分というより、自分の実践が地球と人と呼ばれている、みたいなイメージだ。とはいえ2024年度はてつ(岡田)が入ってきてくれて実践者が二人になったわけだし、自分も風越3年目になろうとしているわけで、「僕の頭の中にあります!」とか「未来について授業しています!」なんてわけのわからないことをいつまでたっても言っていられない。
”地球と人ってなんなの?”この2年間で何度思ったことかわからないが、1年目と2年目では何となく”なんなの?”の中身が違う気がする。
”なんなの?”なんて言ってられない1年目を駆けるなかで見えてきたこと
そもそも入職前に想定していた自分の働き方はふたを開けると実際とは全く違うものだったと思い知る。1年目の春、風越学園に足を踏み入れたとき地球と人の実践者は僕しかいなかった。先代の実践者は卒業していたのである。
・・・何、だと・・・?(心の声)
自分が入職する前まで地球と人の実践をしていたうまっち(馬野)が年度が始まる前に時間をとってくれて昨年度までやっていた教材や資料の引き継ぎ、地球と人の説明をしてくれた。作り込まれた資料とうまっちの言葉から、うまっちは地球と人をつくったスタッフであることだけでなく、他者から親しまれ、信頼されるスタッフであったことは容易に想像できた。
うん、なるほど。わからん。(心の声)
うまっちをはじめ、風越の先輩スタッフからは「ぱわーのやりたいようにやったら良いよ!」と言われた。
そもそも自分は社会科の実践者としてというよりは、授業外での子どもとのコミュニケーションや保護者とのかかわり、スタッフのコミュニティなどにチャレンジの気持ちを持って風越にジョインしたこともあって、心が揺れた。前任校では学校全体の道徳の時間の再設計や生徒支援のあり方について考えてきた。これでは地球と人な日々が待っているのでは…?
そして始まる地球と人な日々。5〜9年生までの地球と人が一気に降りかかってくる毎日だった。これまでのわずかな社会科教員としての経験を頼りに駆け抜ける日々。当時の記憶はあまりない。経験のない小学生を相手にした授業、経験のない90分授業、経験のない地理分野、たくさんの経験のないことを日々つくっていく。特に第1ターム(4〜7月)と第2ターム(8〜10月)は5,6年のテーマプロジェクトのメイン設計者でもあったため、自分の苦手分野であるマルチタスクを余儀なくされる。1、2タームが終わって一息つけるかと思いきや第3ターム(10〜12月)の冒頭にはワールドピースゲームを実施した。
ワールドピースゲームは2023年度当時の7年生と9年生を対象に、5日連続で午前中の授業時間全てを使ってあやさん(遠藤)と一緒におこなったプログラムである。
ゲームのルール上あまり詳しく書けないのだが、僕はファシリテーターとして開始前のルールの読み込みやフィールドの準備、ゲーム中の進行、子どもひとりひとりの行動によって起こる場面の変化、5日間の見通しと介入のバランスなどを担当し、本当に大変だった。自分の授業づくりにはあまり置かない”台本”を読み込みながら子どもの思考や行動を注意深く観察することは、日頃使わない脳を働かせて膨大なエネルギーと時間を費やした。
ここまで書いていて我ながらよくやったなと思う。しかしこうして子どもたちの前に立って共に時間をつくっていくうちに、子どもひとりひとりとの関係性や、学年やラーニンググループなどのコミュニティごとのカラー、5〜9年生までのグラデーションや段階的な育ちが見えてきた。5〜9年生の授業をひとりでつくってきたからこそ見えてきたこれらのことは、現在僕自身が授業を設計したり子どもと関わったり、風越でなにかをつくる上で土台となっている。
”社会のつくり手”
これは地球と人におけるキーワードであり、僕が授業を設計する上で最も大切にしている価値だ。がむしゃらにつくっていく中でいつの間にか手元にあったこのフレーズを、自覚的に授業の中で手渡し始めたのは”偉人総選挙”の実践の頃だろうか。
「偉人を政治家として出馬させて、投票しよう!」偉人総選挙の概要をざっくり言うとこんな感じだ。この実践自体はもともと前任校でも行っていた実践だが、より構成度を限りなく低くして子どもたちがつくれる余白をできる限り大きくした。ワールドピースゲームを終えて社会課題や社会の構造への関心度が高まっている9年生を偉人総選挙における選挙管理委員会に任命し、選挙を通して社会をつくることをともに考えた。結果としてこの実践は幼稚園から9年生、スタッフを巻き込む大きなイベントへと発展していった。


”社会のつくり手”は、奇抜(ふっしぁん(藤山)の言葉)で実は社会科ど真ん中(あすこま(澤田)の言葉)で人間って感じ(あず(栗山)の言葉)と、僕の地球と人の実践を説明する上で必要不可欠なフレーズだ。子どもたちと迷いながらつくった1年目の実践を終えて、何個かの実践と”社会のつくり手”と言うことばが僕に残った。結局のところ、地球と人が何なのかはわからない。
ここまで書いてきたが、僕は孤独だったわけではない。地球と人にはおかつ(竹内)をはじめとした頼れる仲間たちが力を貸してくれた。おかつは2023年度の7年生と8年生の地球と人の時間を短期的に担当してくれた。おかつのつくる授業は構成の練り込み度合いや子どもに手渡す資料のつくりこみなど「自分には出来ねぇ〜」と感じる瞬間が何度もあった。実践者として大先輩でありながら僕の考えや意見も尊重してくれる。こんな大人に私はなりたい。
てつとつくる2年目、てつがつくる地球と人からかたどられる僕のかたち
2024年度、僕が子どもの前で地球と人の授業をしているとき目の端にはいつもてつの存在があった。僕の授業中、てつは時にアシスタントとして、メインとして、臨機応変にその場にいてくれる。僕は授業中に活動を変えたり、用意していたことをやめてその場で新しい展開をつくったりすることがよくあるのだが、そうしたくなった時にはてつのもとへ駆け寄って「今どう見えてますか?」とか「ここのところ変えようと思ってるんですけど」と相談している。てつはいつもてつの視点から助言をくれる。とても頼りになる存在だ。
僕の風越2年目は2024年度に入職したてつに対して、2023年度のはじめにうまっちが僕にしてくれたように、地球と人でなにをしてきたのかを説明することから始まった。
こんな授業したよーとか、子どもたちとここまでつくってきたプロセス、評価の仕組みを伝えた。伝えれば伝えるほど、てつの顔色が曇っていくことがわかった。そうだよね、わかる。
1年やってきたからこそ、まずはてつのやりたいことをやってみてほしいと伝えながら、1年目だからこそ感じるやりたいことをいきなりやる難しさと苦しさの両方があるよなと思いつつ、そう言うしかなかった。
そもそも自分自身に地球と人はこれだという答えを持ち合わせていない中で、明確な道を示せるわけがないのだが、迷いながらつくっていた実践のなかで大切にしたいこととか、見えてきたこととかを共有した気がする。
1年目の自分が感じた苦しみとは違う苦しみをてつは感じていた(る)はずだ。自分は地球と人の実践に対して先代のうまっちがやってきたこととか大切にしてきたことを想像するしかないのだが、てつにとっては目の前に地球と人の実践者がいて実像があるわけだから、その実践自体が地球と人に見えてしまうだろうし、てつ自身の実践と比べることがあるはずだ。それによる苦しさとか葛藤はきっと自分とは違う苦しみなんだと思う。あとは経験年数とか、実践者としては先輩だけど風越としては後輩であることとか色々考えていそう。お互いの教育観とか社会科観を知るために、おかつを含めた3人で相談して2024年度の地球と人の実践は、学年ごとで実践者をわけずに、一緒に授業をつくって2人とも授業の場にいることを決めた。
2024年度が始まって、てつと一緒につくる地球と人が始まった。年度のはじめの方は僕自身の実践にてつが合わせてくれていたり、寄せてくれてくれたりしているように感じた。ぱわーのつくる授業が地球と人で、子どもたちもそれに慣れている。そう見えていただろう。実践していきながら、てつが苦しんでるなとは感じていた。
時間が経って次第に、てつなりのスタイルが見えてきた。ある日の授業で8年生に対して、ぱわーのようなことはできないことや、てつなりの地球と人の時間をてつ自身のことばで語る時間があって、とても象徴的な瞬間だった。
地球と人の実践者、てつ爆誕。
その日以降のてつも苦しみながら地球と人をつくっている印象だが、これまでの苦しみとは違って、てつなりの風越の地球と人を生み出す苦しみのように感じた。てつの想いは授業になって子どもに手渡されていく。次第に8年生の子どもたちもそれに応えるようになって、てつと子どもがつくった地球と人がつくられていった。

てつとの社会科観というか、地球と人観というものと自分のそれは、そんなに大きくズレていないと思っていて、社会のつくり手っていう言葉とか、コミュニティを大切にする視点とか、そういうところは共通しているなと思う。
逆にちがうなと思うところは、それを実現するための手法とかスタイルかなと思う。
どちらのスタイルもいいなと思っていて、僕のスタイルとてつのスタイルが5年生から9年生までの間で体系的に手渡されていて混ざり合ってる感じになっていくといいねと普段から二人で話している。2025年度のチャレンジはそのあたりかなぁ。
二人のスタイルが体系的に手渡されていて混ざり合っていくためには僕らの地球と人がより文字やことばとして外に出て行かなければならないのだが、自分がなかなか文字にしたりことばにすることが苦手なのでとっても苦労している。
この点に関しては、てつに申し訳ないと思っているが、2年目を経て自分自身の地球と人のつくり方というかスタイルがなんとなくイメージは湧いてきた感じがする。
ぱわーの地球と人のつくり方と頭の中
地球と人の授業を設計するときに大切にしている視点は、次のようなことだ。
・授業をする子ども一人ひとりが今どんなことに関心をもっているのか
・授業をするコミュニティの状態やトレンド
・その時期に手渡しておきたいアプローチ方法や探究的なスキル
・扱うべきだったり扱いたかったりする社会科的コンテンツやテーマや知識や見方・考え方
このあたりの視点のどれかを出発点にして設計している。出発点は実践によって異なるが、結果的に僕がつくる地球と人にはこの4つの視点は必ず入っている。特に9年生との授業はこれらの視点が授業づくりに大きく作用している。
2024年度の9年生の地球と人は、理想のコミュニティをテーマにして自分が影響を与えたいコミュニティを分析し、仲間とアクションを起こす”コミュニティ”をテーマにした授業から始まり、価格の決まり方や貨幣の役割、模擬投資などを通して”お金”について考える授業、教室を国会や裁判所に見立てて、子どもたちがそれぞれ役割をもって臨んだ模擬国会や模擬裁判といった”模擬社会シリーズ”、実社会である町に飛び出して軽井沢の人や環境や課題と出会い、課題解決のための方法を考える”軽井沢”の授業の大きく4つを年間通じておこなった(超簡略的な説明)。
こうした年間の活動の中で、これらの視点がどう作用しているのかを書いてみたい。
授業する子ども一人ひとりが今どんなことに関心をもっているのか
この視点は授業一つひとつの活動やことば、手渡す資料に散りばめられている。「マレと休み時間に話したとき、ホームがうまくいっていないって悩んでいたから次の授業はホームのメンバーでコミュニティについてのチェックインをしてみよう」とか、「チーが風越の森の管理について関心を持ち始めたからG(水澤)にインタビューさせてみよう」とか、「ユイがそつたん(9年生の卒業探究)で化粧×心理についてやろうとしているから、化粧品の広告と行動心理の関係についてインストラクションを全体にしてみよう」とか、「タイセイが軽井沢の公共交通機関をテーマに探究し始めたからMaaSについての記事を渡してみよう」とか、言い出すとキリがないのだが、授業の立案から授業中に扱うコンテンツ・出会わせる資料や人などあらゆる文脈で個人にスポットを当てようとしている。それも無理して引き寄せるわけでもなく、歩いていた道でたまたま出会うようなさりげない感じで(上手い表現が思いつかん)。
自分自身の関心ごとや課題意識が社会と地続きである感覚と、手元にある課題に向き合ったり解決のために実際にからだを動かした経験は社会のつくり手になるためにとっても大切なものだと思う。そのためにも一人ひとりが何に関心をもっていたり、授業内外でどんなことを考えているのかをキャッチすることは次の一手を考える上で不可欠なのである。
僕の授業を見学しにきた人から「子どもの活動中、てつやおかつは動き回っているが、ぱわーは何もしていない」としばしば言われる。否定はできないが、きっともう少し高度の高いところで一人ひとりの思考の流れや、からだの動きを観察しているのだと思う。そう言っておいたほうがかっこいい。子どもたちだけの中で起こることをただ楽しんでいる時もある。

風越の環境整備を担当するG(水澤)にインタビューするチー
授業をするコミュニティの状態やトレンド
これまた重要な視点である。授業対象のコミュニティ全体が今どんな状況で、授業内外でどんな経験をしているのか。このコミュニティにどんな活動が手渡されるとおもしろいだろう。十人十色の子どもたちが、集団になった時の特徴やエネルギー、カラーから授業自体の構成度合いや活動のバランスを考える。
例えば2024年度からホームの体制が変わって、子どもの所属とスタッフの配置が一新された。これは年度はじめ「最後の1年」と意気込む9年生たちにとっての大きなトレンドだった。この9年生たちの想いを受け取って、地球と人の授業びらきはホームをテーマにした。子どもたちからは「ちょうど考えたかったんだよね」「これが地球と人?!」なんて声があがった。当初ホームを教材にして授業を構成していたのだが、子どもたちがその壁を突き破ってより広いコミュニティというテーマに押し上げていった。僕は想定していた活動よりもこっちの方が良いと判断したら簡単に準備していたものを手放す。
手放した先で、もはや地球と人の活動を超えて1年間かけてコミュニティについて探究した子どもたちがいる。モミとユキだ。彼女らは自身の関心から1-4年生時のコミュニティに飛び込んで行った。彼女たちは1年生として1日過ごしてみたり、学年スタッフのミーティングに参加してみたりしてコミュニティについて考えた。また彼女たちは異学年で混ざる機会が少なくなっていることを課題として設定し、1,2年生と9年生がまざる時間を計画して実施した。そして彼女たちの探究のプロセスを綴った「コミュニティ探究記」という冊子の作成にまで至った。
準備したものを手放すことで、想定した場所よりも遠くまで子どもたちが行った経験が何度かある。期待を超えられたり子どもたちの力に圧倒される瞬間はワクワクして好きだ。
地球と人の授業以外からトレンドが生まれることもある。9年生全体がそつたんのテーマを設定したと聞きつけて、そつたんのテーマ×経済という授業をおこなった。自身の設定したテーマを別角度で見ることと、テーマと社会の繋がりを調べる活動である。
3学期には、進路がある程度決まってきて、この地を離れる子どもや残る子ども、迷っている子どもに軽井沢の授業を通して、軽井沢との出会い直しをはかった。
また子どもたちの声が授業づくりに反映される仕組みを取り入れている。1年間の地球と人の時間の骨組みとその中身をあらかじめ提案して変更・調整できる機会をつくったり、子どもたちが聞きたい話や、やってみたい活動をおこなっている団体を子ども自身で調べてもらいアンケートで募集、実際にゲストとしてお呼びすることなどだ。子どもたちが地球と人のありかたや学びをスタッフと同じ目線で考える機会を持つことは、学習するコミュニティ全体の傾向を掴むためにも有効だと考えている。

自分たちの地球と人のこれからについて、ちいさくおしゃべりしている9年生たち
その時期に手渡しておきたいアプローチ方法や探究的なスキル
探究に必要なスキルはなかなか掴みどころがなく、子どもに届けたり子ども自身がイメージしたりすることは難しい。しかし風越には探究スキルバザールという探究に必要なスキルが可視化され整理されたものがあり、僕の実践でも愛用している。ちなみに今年度の9年生との時間であがる代表的スキルバザールは「ゆけますコンパス」だ!


「ゆけますコンパス」は主に調査方法に関するスキルバザールで、フィールドワークやインタビューのスキルを指す。地球と人ではこうしたスキルをより構造的に手渡している。共感マップを使って行動観察しようとか、活動中に提示した複数ある視点のうち自分の考えに近いテーマを選んでこのフレームに沿ってフィールドワークをしよう!とかこういった具合である。
地球と人における探究スキルバザールは姿形を変え、時には子どもの探究活動をサポートするワークシートになったり、子どもの成果物を評価するルーブリックになったり、活動自体を振り返る材料になったりする。こうした探究スキルバザールを授業の中で最大限活かしていくために、みっちゃん(大作)との連携は欠かせない。2023年度の僕が地球と人を始める段階からみっちゃんは地球と人の相談相手だ。みっちゃんには授業の構想段階から相談したり、こういう学習をしているんだけどこんな資料が欲しいとピンポイントで相談することもある。時には子どもたちの前に立ってもらって情報への効果的なアクセスのレクチャーや資料の紹介をしてもらう。みっちゃんは僕が構想する授業のねらいや大切にしたいことを丁寧に聞きながらいっしょにつくってくれる、頼れる相棒だ!
扱うべきだったり扱いたかったりする社会科的コンテンツやテーマや知識や見方・考え方
地理・歴史・公民の各領域と、それぞれの見方・考え方は地球と人における活動の基盤になっている。地球と人の活動は社会科を学ぶ中で獲得する枝葉の知識の習得というよりは、幹や根の部分にあたる概念と出会っていくイメージだ。
地球と人以外の土台の学びでも考えられていることだが、いわゆるテストで問われる知識のインプットと風越学園の土台の学びで大切にしている探究的な活動とのバランスは難しい。知識を求める声も一定数の子どもから聞こえてくる。しかし地球と人における学びは個人だけで獲得できるものではなく、隣にいる仲間やコミュニティとの繋がりの中で出会えるものであると、僕は信じている。要望に応じてグループワークなしの集中講義を行うこともあるが(割と好評)。
そして0になる3年目
2年間実践してきてなんとなく見えてきた地球と人だが、2025年度は地球と人を含めた中学生の土台の学び全体で大きなチャレンジがある年である。土台の学びをおこなうコミュニティを学年ごとではなく7,8,9年の異学年でおこなうことになっている。この変化は僕自身が地球と人を設計する上であげた視点のひとつ、”授業をするコミュニティの状態やトレンド”を見極めることがより高度かつ難解になることを意味している。
2024年度に9年生とつくった実践も、9年生というコミュニティだからこそできた実践であるため、これまでのようにはいかない感覚がある。2024年度のコミュニティのような年間を通したテーマになりそうなことばをあえてひとつあげるとするならば、”まざること”は2025年度の大きな柱になりそうだと僕のセンサーは反応している。まざるとかまざらないとか、まざりたいとかまざりたくないとか、社会でも同じようなことが起こっている。実体験と社会的事象の行ったり来たりを”まざる”という視点で考えてみる、そんな時間を構想しているが、例の如く直前でやめちゃうかも。


投稿者力久 聖也
投稿者力久 聖也
佐賀→福岡→京都→鳥取→長野
「安心できる環境って何だろう?」ということをずっと考えています。体を動かすこと、表現すること、聴くこと、おしゃべりすることが好きです。答えのないことについてを 一緒にじっくり考えたいです!