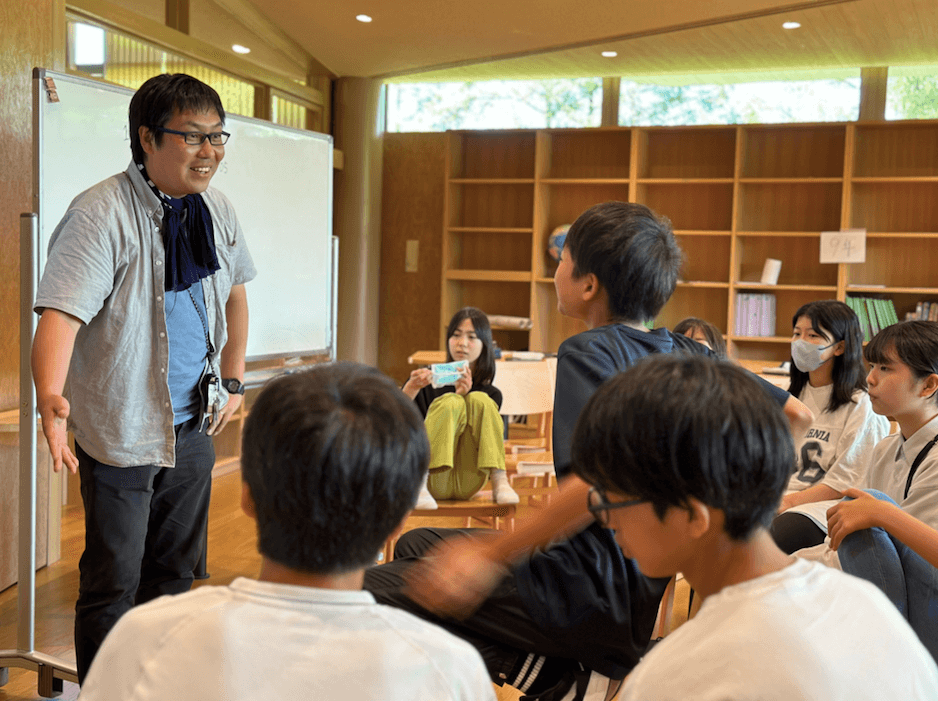一人ひとりがつくり手であり続けられる組織に。(金子 尚矢)

2025年2月25日
私が月に一度程度風越へ行くと、ジョセ(金子)はオフィスでいつも難しそうな顔をしながらパソコンに向き合っていて、その合間に本当にいろんなスタッフに声をかけられ、声をかけ、何かを相談しあっている。そして、その時ふと表情が和らぐのが印象的な人だなと感じていたのだが、その理由が今回話を聞いてみてよくわかりました。(編集部 三輪)
仕事の中で「つくる」を楽しむ。
風越学園が開校する年がちょうど、うちの子どもが1年生になるタイミングで、一保護者として学校説明会に行っていたんです。子どもは隣町の御代田の保育園に通っていて友だちもいたので、御代田の学校に行きたいと結局そのまま公立の小学校に行く選択をしたんですけど、僕が面白い学校だなって思ったんですよね。それで、ご縁があれば事務局とか清掃のスタッフとかなんでもいいから入ってみたいなって思ったんです。

定位置のオフィスにて
__ 前職は星野リゾートで総支配人だと聞きました。観光業界から学校へ、随分と大きなキャリアチェンジですね。
教育の仕事をしたいと思っていたわけではないんですけど、今まで人をマネジメントするよな立場で仕事をしてきた中で感じていた「仕事の中でつくるを楽しむといういう経験をどんなふうにしたら作れるのか」という課題意識と、風越が大切にしていることが自分の中ではリンクして見えたんですよね。それで、子ども時代からつくり手として人が育つ場であり、そこに関わる大人もみんなつくり手であるという風越に自分も関わってみたいなと。開校3年目、人と組織を担当するスタッフの募集があったタイミングで応募して、2023年2月に参画しました。
__ 実際入ってみて、風越の「つくる」はどうジョセの目に映りましたか?
僕は職務上、子どもよりスタッフと関わることが多いんですけど、 一言で言うと、一人ひとりがつくり手になれているというか、つくり手であろうとし続けているのがすごいなと思っています。やっていることが複雑だし、誰かが決めてくれるわけでもないし、 子どもたちも本当に自由だし(笑)。でもその中でも前に進み続けているっていうのが、ものすごい職場だなと思いますね。この世の中にこんな組織なかなかないんじゃないかなっていう気がするぐらい。
当事者だけでは手を伸ばしきれない何かに手当てしていく。
__ 今、いわゆる人事と呼ばれる分野のことをメインでやっていると思うんですけど、ジョセ自身は自分の仕事をどう風越の中でつくっているのかもお聞きしたいです。
難しい質問ですね。自分はここでどういう存在なんだろうっていうのが、そもそもまだはっきりしていない感じがあって。つくるを楽しむという課題意識を持っていたという話をしたのに、僕自身はまだつくるを楽しむという境地に達していないんです。
仕事をどうつくっているかという話でいうと、僕が入った時って人事制度を作るという課題感で採用がかかっていたので、 ソフトとハードというところのハード的なアプローチで何かを良くしていくことが自分の仕事になるかなと思っていたんです。でも入ってみて、そういうハード面に手をつける以前のスタッフが発してるいろんなSOS、それは個人の抱えている難しさもそうだし、チームの状況としての難しさみたいなところをちゃんと受け止めて手を打っていきたいなと思いました。なので、当事者だけでは手を伸ばしきれない何かに手当てしていくっていうことを、この1年半ぐらいは一番意識を向けてやってきたかもしれない。
__ 当事者だけでは手を伸ばしきれない何かに手当てしていく。その“何か”って限りなくあるのかなとも思うのですが、特にこういうところには目を向けるようにしたり、手を伸ばすようにしているみたいなことはありますか。
ひとつは、スタッフに裁量を持って働いてもらえているか、ということですね。風越で働くことの特徴の一つに「協働する」があるんですけど、一人仕事だったら時間やお金をどう使うか、どんな実践をするのかを自分一人で決めて進んでいけるけど、風越ではそうはいかない。だから場面によっては、自分自身もつくり手であると自覚を持ったり、つくり手として自分で自分の仕事のコントローラを持てていると実感するのが難しいということが見えてきたんです。
__ そこに具体的にどんな手当てをしているのか、もう少し詳しく聞きたいです。
たとえば、情報を共有するということを丁寧にしています。予算をこんなふうに割り振ってるよということだったり、 1年間の計画をこんなふうに今やってるよとか、もっと間近な、来週、再来週、今月の計画でなにか調整することある?みたいなこと。組織として動く上で当たり前のことだけど、このカオスな風越だとそういう初歩的なことが意外と情報として流れてなかったり、オープンなんだけどスタッフ一人ひとりの元には届いていなかったりするので。
あとは、僕の見方の癖もあるんですけど、スタッフやチームにマイナスがないかというところを見ますかね。困ってる、何かが進まない、何かによって進めなくなっているというような、そういう詰まってる部分があればそこを解消するようにする。スタッフが、自分や自分たち起点でいろんなコトが起こっていると思えるように、新しいことが起こる、湧き起こるみたいなそういうエネルギーが出てきた時に、そのエネルギーが萎んでいかずに膨らんでいくような場でありたいなと思っています。
__ そういう手当てをする中で印象的だったエピソードがあれば教えてください。
すごくちっちゃいことなんですけど、マイナスをなくすという意味では毎週各ラーニンググループのスタッフが集まって「ナガイモ」という連絡会議みたいなのを始めて。そこで1週間、2週間先の計画を確認したり調整することで、 これ誰が担当するんだっけ?みたいな、誰も握らないフラストレーションみたいものがなくなっている実感はあるかな。
他には、今年度から毎月1回ある研修日の半日を「学びの日」として、スタッフがこのテーマでこう学び合いたいっていうのを出し合って、学びの時間をつくっているんです。半年ごとに前半と後半で期を分けて学び合いのテーマの内容を変えようとしてたんですけど、授業のリフレクションをやりたいと場を立ち上げた人たちが結果的に1年間続けて同じテーマで集まっているんですよ。そこでのやり取りがすごく温かいというか、楽しそうなんですよね。普段のラーニンググループのメンバー以外の繋がりがそこで生まれて、熱量あるやり取りがいつもとは違うメンバーで行われてるっていうのはとってもいい光景だなと感じています。
そういう意味では、自分たちの学びを自分でつくるみたいなアプローチが今年度できたのはすごいよかったなって思うし、研修費も課題としてあった、予算が置かれているけどそれをどう使うのかを誰が決めていくのかというところを、それぞれの学びのチームが自分たちでこういうことにお金使いたいっていうのをと出して、議論して、じゃあこう使っていこうとみんなで決めてやってこれたのは第1歩だったな。
見てもらえているという感覚を。
__ スタッフたちの困りごとに手を伸ばすのがジョセの仕事とのことですが、ジョセ自身が悩んでいたり、困っていたり、難しさを感じていることはありますか?
見てもらえているという感覚をスタッフのみんなに感じてもらいたいなと思っているんですけど、そこはまだなかなかやりきれていないですね。間接的な取り組みではあるけれど、ゴリさん(岩瀬)のリソースをちょっとでも空けて、ゴリさんがスタッフの実践を見に行けたりやり取りできるようにしたりはしているけど、本当は実践以外のところでもそう感じられるのが大事だよなと思うんですよ。それこそ去年は、研修日の最後の1時間は何も予定を置かずにみんなでお菓子とお茶楽しむ時間みたいなのをやったりもしていたんだけど…。
__ でもそれをやめたんですよね。
そう、やめたっていうのか、なくなったっていうのか。こういうことって結果が見えないじゃないですか。よかったなって、いい時間だったなとも思うんですけど、ああいう余白になるような時間を持つことが大事なんだって、僕自身が自信を持ち続けられなかったんですよね。結果がすぐ見えない中で「みんな」を対象にした何かをするっていうことの怖さというか、自信のなさみたいなものもあるんだと思います。そう考えると、スタッフは、毎日そういう中で子どもたちと共に場をつくり続けているんですもんね。本当にすごいなって改めて思います。

あとは、通りすがりに子どもたちのいろんな出来事に巻き込まれるけれど、どう関わるといいのかいつも悩んでいるというか、これでいいのだろうかって思うんですよね、風越にいると。それこそオフィスにいると子どもたちが来て、裏紙ちょうだい、これ印刷して、電話貸してとみたいなことがよく起こるけど、僕らはその子がしている活動のこともわからないし、 その子がどういう日々を過ごしているのかわかんない中で、ぽんと何か反応を返してしまうことへの慎重さや迷いみたいなものがすごくある。
開校して5年が経って、開校当時からいるスタッフと、僕もそうですけど途中から入ってきたスタッフだと、同じシーンでもその迷い具合とか感じ方、考え方が結構違うなと感じることもあるので、夏休み明けからリソースセンターのみんなで集まって、子どもたちとの関わり方とかについて話す時間を持っています。別にみんなが同じ関わり方をしなくちゃいけないわけではないけれど、ずれをちゃんと言葉にするとか、確認し合うっていうことが今のリソースセンターには必要なんじゃないかなと思って。教員以外のスタッフもみんなが子どもと関わるからこそ、そういうやり取りも大事だなと。
つくり手であり続ける組織はどんなふうに作っていくといいのか?
__ 最後に、ここから思い描いていることやチャレンジしたいと思っていることをお聞きしたいです。
自分自身が持っている経験をどう風越で発揮するといいのか、2年間色々試したりはしているんだけど、やっぱりまだはっきりとしてこないんです。あんまりこうだって決めすぎず、頑なにならずに、いろんな探りながらいる感じをある意味大事にしてきたからだとは思うんですけど。
__ もうしばらく探る時期が続きそうですか。
それをどう運営していくのかということの議論を重ねているところなんですけど、一人ひとりの力が発揮できたり、人が繋がっていけたりするような制度をつくれるといいなと思っています。1発目から良いものはできないかもしれないけど、仮でも置いてみて、やってみて、どう変わっていくのかということは、ここから見ていきたいなと思ってます。
僕が風越に入る時の採用試験で、「問いはなんですか」という課題がありました。僕は、「(仕事に)関わる全ての人が”つくり手”であり続ける組織開発は可能なのか」という問いをおいたんですけど、風越は今、開校から5年、6年目を迎える中で、スタッフ一人ひとりが自分(たち)からつくるということを働きかけていかないと、 つくり手にはなれないフェーズにも入ってきてると感じています。色んなことを整理して整えると、 一見、効率的になっているように見えるけれど、つまらなくなったり、考えなくなったり、安定であることを守りたくなったりする。どこかのタイミングで何かを壊すみたいなことを、 大人も恐れずに問い続けたり、挑戦し続けることはこれから必要そうだなと。
でも、全部が整わなすぎても消耗するだけなので、人が良いエネルギーを発揮するための安心してできる領域というか、考えなくていい領域がどこまでなのかっていうことは、考えてアプローチし続けたい。でもその領域って常に変わると思うので、そこにいかにスタッフみんなで自覚的でいたり、楽しんだりすることができるのか。風越学園が次のフェーズに入ってるきている気がするので、今までとは違う味わい方をみんなでやっていけたらなと思ってます。
__ 味わうっていいですね。
うん、やっぱり楽しいことだけじゃないので、色々含めて味わっていけるといいのかなと思います。
インタビュー実施日:2025年1月24日

投稿者金子 尚矢
投稿者金子 尚矢
御代田に住んで10年。息子たちをきっかけに地域のいろんな人に出会い、人に出会うほどにこの地域が好きになりました。
風越学園でも子供を中心にして、いろんな人との出会いを楽しみにしています。