チャイムから風鈴へ。
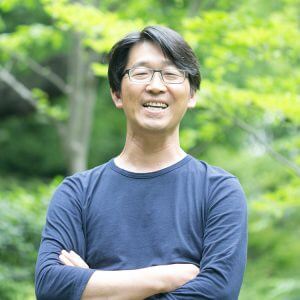
2025年8月27日
江戸・日本橋から長野を抜け、京都・三条大橋を結ぶのが中山道。全行程は、135里32丁(約534km)で、碓氷峠をはじめとして峠が多く、69もの宿場があったのが特徴だ。このうち、軽井沢町には東から順番に軽井沢宿、沓掛宿、追分宿と3つの宿場があった。
中山道も含めて江戸時代に整備された主要な街道には、一里(約3.93km)ごとに目印があった。この目印が一里塚だ。街道の両側に土を盛った「塚」を築き、そこには榎(えのき)や松が植えられた。旅人は、この一里塚を距離の目安にしたり、休憩場所にしたらしい。

国道18号線から見える追分宿に近い一里塚

「追分の一里塚」という看板が立っている。
設立準備中の2017年5月15日に第1号を発行したメルマガ・かぜのーとは、今回の2025年8月28日発行の第100号で区切りをつける。メールマガジン発行の素材となる記事は、こんな編集方針のもと綴られていった。
子どもたちの遊びと学びの様子、日々生まれるスタッフの問いや気づきなど、学校づくりについてなるべくそのまま正直にお届けします。
この編集方針は昔も今も変わらない。スタッフ一人ひとりが書いた記事をWebに掲載していき、一ヶ月に一度それらの記事を紹介しながら、軽井沢風越学園のいまの音や流れを、書き手の思いを乗せて、写真のように切り撮ったり、動画のように区切ったりして伝えてきた。風越に関心を寄せてくれている人たちに、自分たちのいまを自分たちの手で届ける。それが、かぜのーと。一里塚は、旅する人たちの行く先の印になったと同時に、その旅を思い返すときの印にもなっていたに違いない。メルマガ・かぜのーとも、風越にとってそんな存在だ。
先日、あるNPOの経営陣の一人であるSさんとゆっくりやりとりする機会があった。Sさんは、そのNPOで長くパブリック・リレーションズも担当している。Sさんは、「パブリック・リレーションズ」という言葉を「PR」と省略したり、「広報」と言い換えたりしない。そして、パブリック・リレーションズの仕事についてこう語っていた。「パブリック・リレーションズの仕事は、内側と外側をつなげていくこと。そのためには内側を変えていく必要もある。言ってることとやっていることを一致させることが大切。その上で、誰もがわかるかたちで公式見解としてメッセージを伝える。」
そう、かぜのーと編集部が力を尽くしてきたことは、このパブリック・リレーションズだった。決して風越のプロモーションではない。「なるべくそのまま正直に」という姿勢で内側と外側の関係をつくり続ける。そんな仕事をしてきたのが、かぜのーと編集部だ。だから、記事の原稿がやっていることと食い違っている場合は、容赦なく修正提案をばしばし入れていた。最終的には発信しないと判断した記事もたくさんあった。「書いてみたいが自信がない」というスタッフには伴走もした。「発信してみたらいいんじゃないかな」と感じる実践があった場合は、「書いてみない?」と声をかけて歩いていた。「かぜのーとの記事を書く」というのは、風越のスタッフにとっては仕事の道標を示す「一里塚」でもあったのだ。
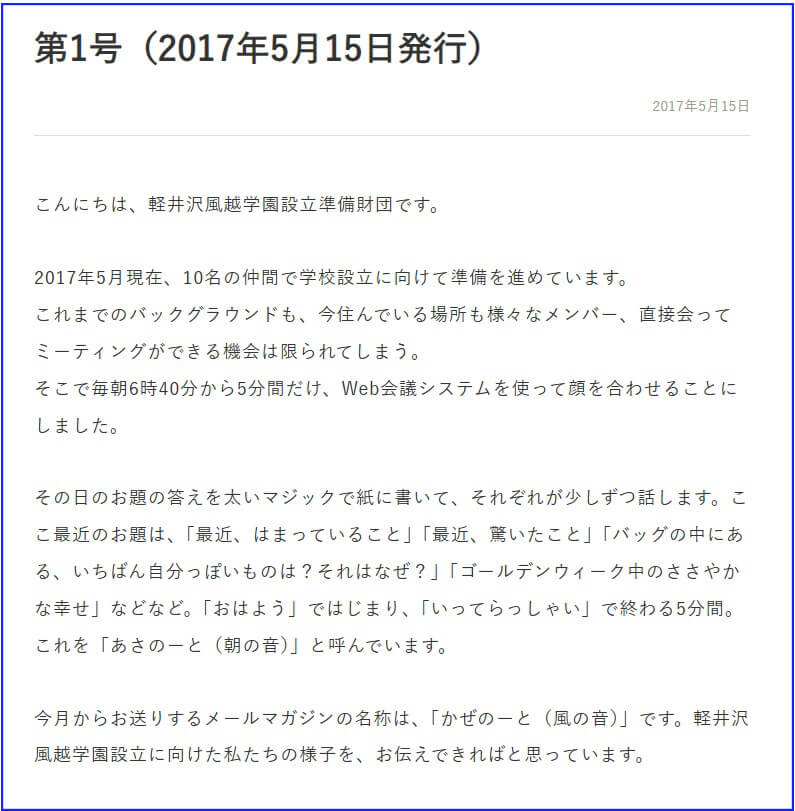
(2017年5月15日に発行された第1号のまえがき)
情報と情報とを関係づけて、人と世界の可能性をひらいていくのが「編集」という仕事だと思う。そんな編集の仕事をていねいに続けてきてくれたかぜのーと編集部のふたり、ありがとうございます。引き続き、よろしく。
第1号のメルマガに書かれているように「かぜのーと」は「風の音」。愛読者のみなさん、月に一度、定期的に音を届けることはなくなりますが、風越ではいろいろな音が奏で続けられています。その音を、これからもWebで伝えていきます。風越ではチャイムは鳴りませんが、月一回のメルマガはチャイムのような存在だったのかもしれません。これからはInstagramへ移行します。風が吹いたときに鳴る風鈴のように、さまざまな音を届けていきます。これからも風の音に耳を澄ませてください。
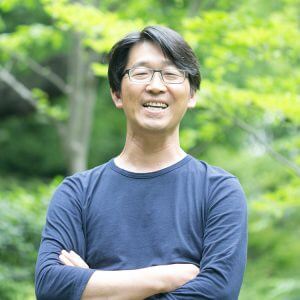
投稿者本城 慎之介
投稿者本城 慎之介
何をしているのか、何が起こっているのか、ぱっと見てもわからないような状況がどんどん生まれるといいなと思っています。いつもゆらいでいて、その上で地に足着いている。そんな軽井沢風越学園になっていけますように…。
詳しいプロフィールをみる

