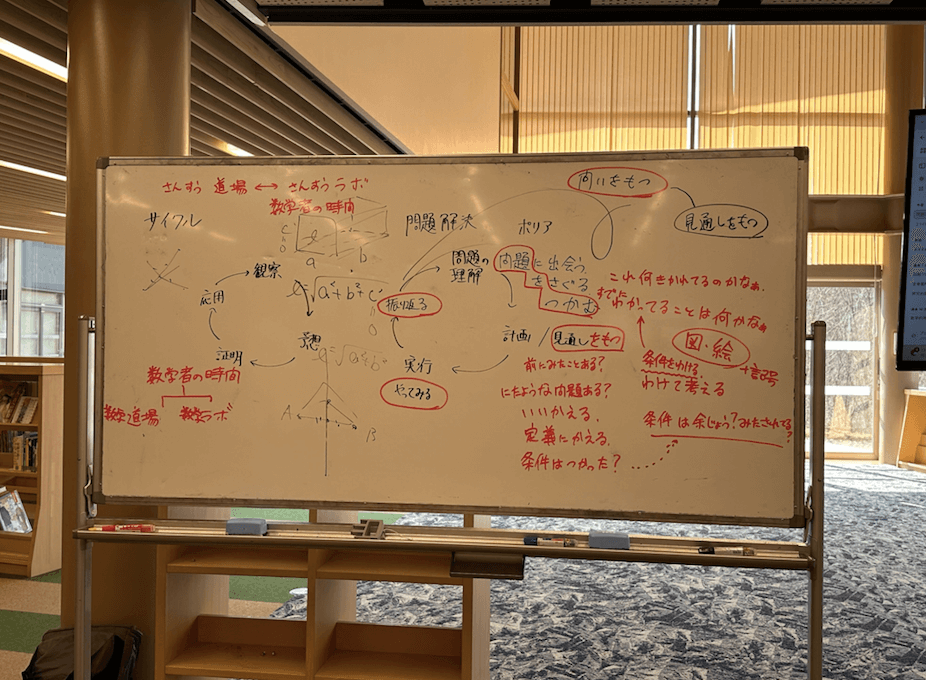問い続ける身体ー「フクシマを持ち寄ろう」

2025年5月6日
東日本大震災、オキナワ、水俣病、ハンセン病。りんちゃん(甲斐)と中学生の国語の授業は年に数度、骨太な社会問題をテーマに単元学習が進んでいく。
2024年度は8,9年生で「フクシマ」をテーマにしようと思っていて、とりんちゃんから聞き、かぜのーと記事に残したいと思った。ちょうど女川原発の再稼働のニュースが流れてすぐのタイミングだった。
国語の授業の中で社会問題を扱うことについて、りんちゃんは以前こんなふうに語ってくれた。
国語は「私」が大事な教科。短歌や随筆などアウトプットの手法は色々あるが、究極的には「私」という存在をどう捉えるかを表現しなくちゃいけない。でも「私」を表現することが苦しい子たちもいる。社会的課題はどのような教科であっても「人間」と向き合うことになり、「私たち」を意識し、見つめ直すチャンスにもなります。そう考えて公立中学校で教えていた頃から社会的課題をテーマに据えて授業づくりをしてきました。
風越学園にきてから、ネパールの人たちの仕事づくりを30年以上続けてきたネパリ・バザーロの土屋春代さんと出会い、次世代を担う子どもたちに授業を通じて社会の問題を伝え続けてほしい、教員はそれができる仕事だからと言われたことで、そうだなと改めて思いました。

今回の「フクシマを持ち寄ろう」は当初、9年生のみ対象とし、7,8年生は「ヒロシマ・ナガサキ」にしようかとも考えたという。しかし、8年生の時点で心を動かしながら授業に取り組む経験をしていることが、彼らが9年生になったときに生きるのではと、8,9年生で実施することになった。ふだんの授業は学年別だが、最終的な成果物となった学習記録集には8,9年生全員のアウトプットが読めるようにまとめられた。
学習記録集の目次は、次のとおりである。
- 単元 フクシマを持ち寄ろう 〜問う・問い続ける〜
- 『ノーニュークス』(講談社)より「カタカナの街」重松清他
- 読書リスト(紹介) 読書記録
- 学びの設計図
- 坪倉正治先生(医師・福島県立医科大学放射線健康管理学講座主任教授)との対話
- アウトプットを考える 決める
- アウトプット作品・資料(自分・友達)
- 発表文字起こし(8,9年生 全員)
- あとがき集
10月下旬、8年生に向けた単元びらきの授業で、りんちゃんはこんなふうに語った。
今回、一番大事にしてほしいのは自ら「問う」ということと、「問い続ける」ということです。
たとえば小さな子どもが「どうして空は青いの?」と大人に尋ねる時、本当になんで青いんだろう?と不思議に思っている。誰かに問うてごらんと言われたわけではない、身体の中から生まれている問いですね。みんなには、問うことで考えが深まること、本当に身体から湧いてくる問いと出会う経験をしてほしい。「問う」「問い続ける」力は、9年生になってから取り組むそつたん(卒業探究)にもつながります。
調べてみて「わかった」とか上手にまとめるということじゃなくて、わかった後に自分はどう思う?自分はどんな未来を描くの?などと、言葉にしていくのが国語科です。本当に問いたいことを探していく単元にしていけたらいいなと思っています。
いろんな文章の中で心に留まった箇所をメモして、問いを立てましょう。出てきた問いにすぐ答えようとするのではなく、問いを貯めていきます。そうやって貯めた問いから、本当に考えたいことが浮かんでくるんじゃないかな。
まずはさまざまな文献や本・情報に出会い、さらに東日本大震災直後から福島県に入り、医療活動を継続しながら相馬市や南相馬市で内部被曝検査に取り組んできた坪倉正治先生から話を聞き、子どもたちは深めていくテーマとアウトプットのかたちをそれぞれ選んでいった。
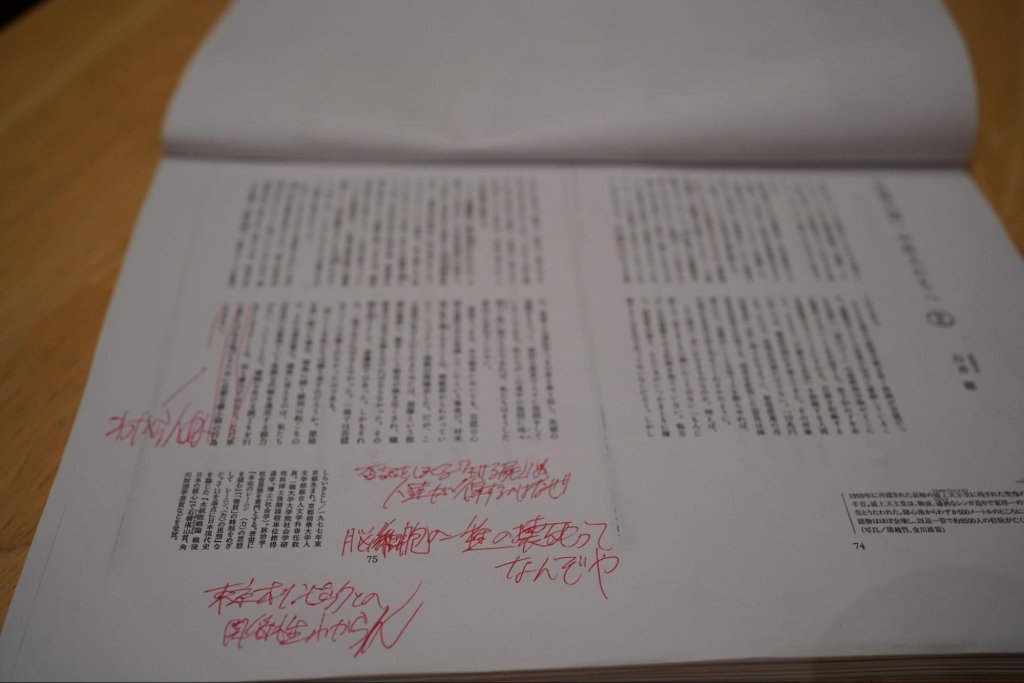
「フクシマ」の授業をつくりながら、りんちゃん個人の探究テーマとしては「国語科の単元学習と探究がどこでどう重なって、どこでどう違うのか?」という問いが傍にあった。国語科の授業の中で、探究的要素をどのように重ねればよりよくなっていけるかという問題意識から生まれた問いである。
単元の終わりに提出するアウトプットの方法を授業者が決めずに子どもたち自身で選ぶことが探究的要素の一つだと考え、今回はそのようにした。随筆、物語、詩、絵、図式化、新聞形式でのまとめなど、子どもたちは自分なりのやり方で「フクシマ」に向き合っていた。
しかしアウトプットの方法を自由にするならば、アウトプットに至るプロセスで子どもたちの考えが深くなっていく、問い続けることを体験していくチャンスを逃さないことが大事だったと、特に8年生のアウトプットにフィードバックしながら痛感したという。
私のねらいとしては、深掘りしながら問いながらアウトプットに向かっていく想定だったが、調べたことをまとめることや見せ方に時間を使ってしまい、問いが深くなるチャンスを逃している感じがした。
もちろん読み手に伝わるように工夫してほしいが、きれいに上手に伝わることが大事なのではない、ということが徹底できなかった。学んだり感じたりしたことを言語化していく時に、パソコンを持ってきて(例えばCanvaでの見せ方を)どうしたらいいか?と工夫を尋ねられる。デバイスでドキュメントをつくるときの彼らが、深堀りする身体になってないように見えてしまう。デバイスでの作業の前の、あるいは作業中の対話を再検討することが必要だと思った。
子どもが言葉を生み出すプロセスに関わりたい。大切なことは、その子を一段上に引き上げること。一人ずつその段階が違うからこそ、届く言葉がある。この子にしか届かない言葉で、その子に関わることができる。今回もそうしたいと思っていたのに、アウトプットを自分たちで選んだら、それが手元から離れていく感覚があった。
8年生と9年生では一緒に過ごしてきた時間が違うから、8年生へのフィードバックには少し遠慮してしまってとりんちゃんが言うので、Google classroomのやりとりを覗いてみると、じゅうぶんまっすぐに伝えているように見えた。
フクシマの作品受け取りました。随筆というジャンルを選んではありますが、今回大切にしている「問う」「問い続ける」という部分が少ないように思います。
SD(編集部注:7年生で行ったセルフディスカバリー)の随筆を思い出してほしいのですが、「事実」をきちんと叙述し、そこから自分の中に湧き出た思いに問いを立てながら自分の心の中にある言葉と向き合う作業が必要です。
「とても興味深い作品だった」という記述には、「問う」に対する自分なりの答えがないように感じました。どう思いますか?少し話せればと思います。
ただそれが受け取られたかどうか、なのだろう。同じことを伝えても、9年生は「どういうことですか?」と問い、8年生は「なんでだめなんですか?」という受け取りになったという。問い続けられる力と、誰かからの問いやフィードバックを受け入れる身体はつながっている気がする。
1月下旬、仲間のアウトプットに耳を傾ける子どもたちの姿があった。9年生の言葉を紹介したい。

「原発の代替ってあるの?」というテーマにしたのはコタだ。発表では、次のように話していた。
「原発のない世界のつくり方」という本を読みながら原発なしでも社会は成り立つのか?という問いが生まれた。反対派の意見もそうだなと思うけど、代替案は書かれていなかったので、あんまりしっくり来なかった。反対派は事故が起きた時のことを理由に反対していて、賛成派は原発がなくなったときに起きうることを懸念している。能登の地震の後、原発に関する定期調査で反対派が増えたらしい。
再生エネルギーだけでは原発の代替にはなり得ない。今後、最強のエネルギーが生まれてほしい。
<そして「フクシマを持ち寄ろう」の学習記録のあとがきに、コタは次のように書いた。
フクシマについての学習を終えてみて感じたこととしては、原発問題の難しさだ。
(中略)
原発をなくすか、再稼働するか、これはすぐに解決できる問題ではないと思う。そして、印象に残ったこととしてはある教授の論文だ。彼は、人々は原子力発電の事故を懸念するが、原子力発電がなくなった未来も懸念するべきだと述べていた。もちろん原発の事故というものはとてつもなく、ひどいものである。しかし、それを考慮しすぎてなくしたあとを考えていないというのは僕も感じるものであった。だからこそ原発問題はすぐに解決するものではなく、とても難しいものだ、と感じた。
解決策というものは、僕の知識では正直何もわからない。だが、わからないという理由で深刻な問題を放置するのはいかがなものかとも思う。だからこそ今回の「フクシマを持ち寄ろう」で、知識を入れることができてよかった。
この学習の前に何となく思っていた「難しい」と、終えたあとにコタの中にある「難しい」の内実は、きっと変化しているように思う。

モミは、アウトプットの形式に物語(小説)を選んだ。被災者の友達を主人公とし、第三者の視点で東日本大震災について語る物語を創作した。モミの学習記録のあとがきには、次のように書かれていた。
東日本大震災は、小説などのテーマで取り上げられることも多い。だからだろう、私はすっかり知っている『つもり』になっていた。
でも、そんなの嘘だ。私は東日本大震災について何も知らないのだと、思い知った。事実だけならば、辛うじて言葉にすることも出来る。しかしそれは、どこかで聞いた、ただの薄っぺらい情報に過ぎない。
家、町、ふるさと、家族、命ー沢山の宝物を失った人たちが、かつて、そして今どのような思いを抱いているのか、私は知らない。
作中に、「俺にはそう言うことしか出来ない。不用意に言葉を選ぶ資格が、何も知らない俺にはないからだ。」「何と言えばいいのか、俺には分からない。きっと、何を言っても嘘っぽくなってしまうだろう。」と言う文章があるが、これは私の心の声でもあるのだと途中で気がついた。
どうしてこんなに薄っぺらいんだろう。どうしてこんなに嘘っぽいんだろう。私はずっと問い続けていた。
どこかで、それは体験したことがないからだと言い訳にしている自分もいた。今は思う。「体験したことがないから」それを言い訳にするのではなく、まずは知ろうとすることが大切なのだと。
今回、フクシマの単元で学んできたことは、世の中に溢れかえる情報の、ほんの一握りだ。でも、もっと知りたいと思える機会になった。
少しずつ事実を知っていく中で、生まれる問いも増えていった。
「東日本大震災に終わりはあるのか?」「家族を失ってしまった人は、今どのような思いで生きているのだろうか?」「本当に生活が元に戻るとは何なのか?」「そもそもそんな時は訪れるのだろうか?」
問いが生まれるというのは、興味を持っている証だと私は思う。
その問い達は、考えきれず、今もまだ宙を彷徨っている。でも、そこで問いを放棄するのではなく、考え続けたい。まずは現実を知ること、それを考えること、そして自分ごとにしていくことが、大切なのだと知ったから。
問い続けるということが身近になるといいな、問い続けて考え続けてほしいというりんちゃんの願いを、子どもたちは受け取っていたように思う。
りんちゃんからは、どう見えていただろう。
9年生のアウトプットやその発表では坪倉さんの話を引用している子たちが多くいた。脳内に繰り返しそのことがよぎってくるとか、引用できるということは、考え続けている人ができること。
答えを出すことだけというよりは、考えようとする人を育てたい。考えもしないで答えを探していると、朗らかになれない。頭じゃなくて身体が自然と考えちゃってた、という人になっていけるといいよね。
では、りんちゃん個人の探究テーマ「国語科の単元学習と探究がどこでどう重なって、どこでどう違うのか?」という問いは、その後どう変化したのだろう。
最初に問いを立てたことによって、実践の度に「どう違うんだ?」と問い続けていました。問いを立ててよかったなって思います。でも結局はその違いを明確にするというより「風越という場所でこそできる国語科の授業はどんなものだろうか?」という問いに変わりました。
風越学園が「つくる」ことを大事にしていることともつながっていると思うんだけど、風越の子どもたちの姿の一つとして、発想の自由度が高いなと思う。そして「私」という存在に対する自覚度が、年年高くなってきている。つまり、学びをつくっていく上で「私」という存在がすごく大事な概念としてあるということに気づいている感じがしています。
国語科に限らず、話す・聞く・話し合うという場がとっても豊かで、他者の声を聞く機会がすごく多いという環境の中で、子どもたちは学んでいる。
であるならば、国語科の授業の中で、他者の声を聞く機会が意味あることなんだっていうことを言語化したり、自分が他者の声を聞いたことによって何が開かれたのか?、あるいは何が獲得できたのか?ということをちゃんと言葉にする、そういうことが大事なんじゃないかなと思っています。
友だちの話を聞くこと自体が自分の力にもなる、そういう学びに向かっていけるといいなと思っています。
2025年度、7〜9年の土台の学びは異学年をまぜて実施することになった(過去2年間は、学年ごとに分かれて土台の学びを実施)。まざることで起こる学びの可能性を以前からずっと話していたりんちゃんの授業が今年度どんなふうに変化していくのか、私もまた一緒に授業にまざってみたい。(かぜのーと編集部・辰巳)