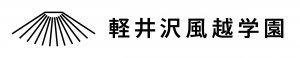<自由>と<自由の相互承認>の感度を育むことが、本当に教育の原理なのか?
(第1回風越コラボレポート )

2018年7月19日
6月30日(土)に第1回風越コラボを開催しました。第1期は、首都圏以外にも長野、山形、大阪など各地から集まった60名が参加しています。初回のこの日は、「<自由>と<自由の相互承認>の感度を育むことが、本当に教育の原理なのか?」を問い直しました。
予め、苫野の著書である『教育の力』と『どのような教育がよい教育か』を読み込んできた参加者たちが、グループに分かれてどんなふうに本を読んだか、どんなことを聞いてみたいかを出したあと、どうしてもこの場で問いたいことについて、苫野とやりとりしました。

その中から一部を抜粋して、ご紹介します。最初の口火を切ったのは、山梨から参加の大学院生です。
ー誰もが生きたいように生きたいという自由への欲望を持っていることについては、納得しました。場合によっては、人は死にたいという欲望も持つと思いますが、それは認められるのでしょうか。これが認められると、<自由の相互承認>の原理はどうなっていくのか、自分の中でもやもやしています。
苫野:いきなりものすごい問いが来ましたね、ありがとうございます。
まず、自由への欲望はいろんな形を持つものです。自分で自分の満足いく生がなければ、終わらせたいという欲望は、自由への欲望の一つの最終形態と言えます。また、それがうまくいかない場合、できるだけ人間的な欲望をなくして動物のように生きるというのも、自由への欲望の一つの現れ方です。
さて、<自由の相互承認>の最終審級は、社会的な合意にしかありません。つまりどこまで互いの自由を認めるかについては、社会の合意に委ねるしかないんですね。認められるかどうかという問いではなく、また絶対に正しい答えがあるわけでもなく、どのような場合において、どの程度認めるかをみんなで対話し、考えあっていくしかない問題だと思います。
人間的な欲望である”自由”
ーそもそも私たち、私自身が自由なのか、自由だとすればどのように判断すればよいか考えてみました。多くの人が不自由でもないが、自由だー!と叫ぶ感じでもない、その中間あたりにいる気がします。すっげー自由だよ!とも言えないし、むちゃくちゃ不自由でもない。不自由です、と思い当たるものをいくつか挙げられない人は自由といえるなら、私はそこそこ自由かもしれません。
子どもたちと、自由についての話をすると、なんだか硬くなってしまう。そこで、気持ちいいか・気持ち悪いかということで話をしたことがある。自由と気持ちいい、あるいは不自由と気持ち悪いは同じと言っていいのか、あるいは違うのかについて、聞いてみたいです。
苫野:気持ちいいは、自由の内的感覚のことですね。つまり、自由を感じているところには、必ず気持ちいいという感覚がある。
でも、その逆は必ずしも真ではありません。つまり、気持ちいい時は必ず自由だというわけじゃない。これは幸せも同じです。たとえば私たちは、温泉につかったときに幸せだ、気持ちいいと言いますが、自由だとはあんまり言わない。つまり、気持ちいい、幸せだという言葉は、比較的動物的な欲望がかなった時にも使う言葉であるのに対して、自由はより人間的な欲望がかなったときに使うのではないかと思います。
しかし我々は、生きていく上でただの気持ちよさだけを求めるわけではない。やっぱり人間的な自由を求める。生きたいように生きたい、というのは、人間的な欲望ですよね。そういう関係性なんじゃないかなと思います。
子どもたちが自由を獲得するための制限
ー子どもたちが自由を学ぶためには、自由を制限することが必要とのことだったが、大人がどこまでの基準やどの程度、制限すればいいかが難しいと自分なりに感じています。無自覚に子どもたちに言うことを聞かせるように子どもたちに接している教員もいると思います。どんな教員でも、この程度のレベルの自由まで認めてあげたいというのがあるのかどうかを聞きたいです。
苫野:まず、自由は制限される必要があると言うと、自由な教育を求める人は、ん?と思うかもしれませんが、実はこれはすごく大事なことなんです。市民社会は、私たちは誰もが相互承認を理解しているんだよね、という信頼の中で初めて成り立ちます。しかしまだそこまでの認識がない子どもの場合は、自由は一定制限され、その代わり特別な保護と教育のチャンスが保障される。子どもたちは何でもかんでも自由にしていいわけではない。私たちがつくろうとしている軽井沢風越学園も、自由な学校という以上に、自由になるための学校と考えています。
じゃあその制限はどこまですればいいかは、成長に応じて都度考えるしかありません。子どもはまず、親からルールが与えられます。でも成長するにつれ、だんだん自由の感度が高まって自由になりたい欲望がうまれ、そこで初めてルールとの葛藤が起こるのです。もし制限がないと、そもそも我々は自由になろうとも思いません。自由への欲望は、制限があるときに自覚するのです。ですから、ある程度の制限は程よく必要で、先生や親との葛藤を通して、自分が自由になるためにはどうすればいいかを考える。その意味では、そうやって子どもたちが自分で考えることができる自由は、学校に必ず必要です。
そのようなバランスをとる教師って、本当にすごい仕事だなと思うんです。自分の関わりや今の制限は、子どもたちの自由のためになるんだろうかと常に問い直しながら実践できるかどうか。それを都度考えられるのが、先生の力量になってくるのだと思います。
ーそういう自分じゃいけないなと思いつつ、私はどちらかというと子どもたちを恐怖で支配するタイプの先生で。でも葛藤の中でこそ自由への獲得を自覚するということであれば、自分でも工夫できそうだなと思うことができました。
苫野:学校全体がチームとして、実践できるといいですよね。この先生は厳しいけれど、この先生は自由にやらせてくれるな、という、生徒にとっての学校全体のバランスを考えることはすごく大事。そもそも社会って、そういうものですよね。

価値観の対立を越える原理
ー大学で、留学生に日本語を教えています。公教育での<自由の相互承認>を考える中で、日本に住む外国人ももちろんそこに入るべきだと考えていますが、日本人の学生のことしか考えていない、場合によっては、留学生の自由を侵害してしまっていることがよくあります。その人の価値観は変えられないと思うが、どうにかして留学生、外国人も含めた<自由の相互承認>ができる場をつくりたいと思っているが、どうすればいいでしょうか。何か考えがあれば聞かせてください。
苫野:私は哲学徒なので、何のために公教育が必要かという原理、本質しか言えません。なので私ならば、大学も公教育の一つで、<自由の相互承認>の実質化をするために在るんですよと説き続けることしかできないですね(笑)。あるいは、みんなにとって心地のいい空間ってなんでしょう?ともう少し柔らかい問いかけもありうるかもしれません。
原理を共有することは非常に大事で、価値観や信念のレベルではどうしても対立が起こってしまいます。多様性を大事にしようという人と、ここは日本だから日本のルールに従うべきだという人の対立は、おさめようがありません。そこで、原理が必要です。公教育は、自由を相互に承認しあい、一人ひとりが自由になっていくためのものであるという原理が納得されれば、そのためになにをすればよいか、信念ではなく、原理のレベルで考えあっていくことができる。そういう意味で、私なら大学に原理を語りますね。
ーありがとうございます、がんばります(笑)。
<自由>と<自由の相互承認の感度>の指標
ー授業のやり方自体は実践理論なので、たとえば一斉授業をやれば<自由>と<自由の相互承認の感度>は高まっていないとか、グループワークだから高まっているなどとは、一概には言えないと思います。また教員は哲学者じゃないので、現場で公教育の原理として成り立つかどうかをきちんと考えていくためには、<自由の相互承認の感度>が測定可能なものである必要がある気がします。そうでなければ、現場の教員にとっての原理になりにくいのではないでしょうか。<自由の相互承認の感度>を測定可能なものとしてイメージされているのか、そうじゃないのかを聞きたいです。
苫野:一定の測定は可能だと思います。実はいま、その指標づくりと測定研究を共同で始めているところでもあるんです。相互承認の感度は、いくつかの段階があるように思っています。「どんな価値観や感受性の持ち主も、他者の自由を侵害しない限り認めることができる」は結構高いレベルです。また、「自分の価値観や感受性は、他者からの普遍的な承認を得られない限り正しいとは言えない」というのは、ある意味では最高レベルの相互承認の感度と言えるかもしれません。
問いとは、生きていれば自然に生まれるもの
ー苫野さんにとって、問いとは何でしょうか。問いを立てるうえで大事なポイントは何か、また子どもたちの問いの立て方を教えるとしたら、どのように教えるとよいか聞かせてください。
苫野:私自身は、子どものときから、なんで生きてるんだろうとか、何のために生まれてきたんだろうと、本気で悩んでいました。幼児の頃から、生が苦しくて苦痛だったんです。だから私の場合は、苦悩から問いが生まれた部分が大きいですね。
アメリカの教育哲学者ジョン・デューイは、シチュエーションから問いが生まれる、と語っています。だからこそ、自然に問いが生まれる本物のシチュエーションを教育の現場につくりましょう、といったわけです。決められたシチュエーションばかり用意して、どんな問いを立てるかも決められていることは、人間にとって不自然なんです。人間の探究、経験とは、問題状況に直面し、それを解くというプロセスの繰り返しです。つまり問いとは、生きていたら自然に発生してくるものなのです。
それが苦悩であれ、わくわくしたいという動機であれ、経験すること、生きることは、それ自体が問いを立てること。子どもたちは、たいてい切実なシチュエーションの中に生き、常に問いに満ちているので、大人はただそれを尊重する。デューイは、子どもは学びたい欲求や知りたい欲求、作りたい欲求、コミュニケーション欲求などの本能的欲求を持っているが、学校に入った瞬間に殺されてしまう、とも書いています。自然に生まれた問いを探究していきたいという欲求が、学校という決められた空間の中でどんどん殺されていく。そうでなく、子どもたちの探究をベースにした教育をつくろうというデューイの100年前の提案は、今でも生きていると思っています。
多様性を担保する公教育への構造転換
ーこの場は、事前に苫野さんの本を読み基本的な前提を共有している人たちが集まっているので、相対的に同質性が高い。でも本質的には、そこを越えた異質の人たちとどう相互承認をしていくかを考える必要があると思っています。自由の相互承認の感度を高めていったときに初めて公の成熟があり、学びの中で一人ひとりが異質性をどう越えていくかが本質ではないでしょうか。
苫野:承認は、非常に幅がある概念なんです。高く称賛する承認もあれば、存在だけは認めることも承認。ニーチェは「愛せない場合は通り過ぎよ」と言っていますが、これも一つの承認です。愛せないからといって攻撃するのではなく、通り過ぎつつ、存在だけ認める。でも、それでいいと思うんです。相互承認というのは、すべての市民が対等に自由な存在であるとお互いに認め合うという約束であり、どの程度認め合うかは、その場その場に任せられています。
一方で、なぜ相互承認が大事かというと、一人ひとりが異質だからだということです。異なる価値観を持ち、異なるものを追求すると、必ずぶつかりあいます。でも、他者の自由を侵害しないのであれば、まずは認めあう。それができるためには、多様な人たちと出会って相互承認する経験を豊かに持たなければなりません。そして、この機会を本来は教育がつくらなければいけないのです。かつての教育は、ある程度このことが実現できていました。公教育が始まった時代には、子どもたちは親や村の価値観がすべてでした。でもそんな子どもたちが学校にくると、ある程度多様性の中に投げ込まれることができた。生まれも育ちも違う子どもたちが集うことができたのです。ところが現代は、学校が新しい習俗になり、非常に同質性の高い場所になっている。もう一度、公教育を多様性がごちゃまぜの、異なる価値観同士が相互に承認しあう経験を積む場に転換していく必要があると思っています。
「信念補強」ではなく「信念検証」の原理
苫野:最後に、〈自由〉と〈自由の相互承認〉という原理を手にすると、かえってそれを自分の信念を都合よく補強するのに使ってしまうことがあることに注意しておきたいと思います。自分の実践は、〈自由〉とその〈相互承認〉を実現するものになっているんだ、あいつのはそうじゃないんだ、と都合よく使ってしまったり。
でも大事なのは、「信念補強型の思考」ではなく、「信念検証型の思考」です(これは私の師匠の竹田青嗣の言葉です)。自分の実践は、本当に〈自由〉とその〈相互承認〉を実現するものになっているんだろうか。そう問い続けることが重要です。
そしてもちろん、〈自由〉と〈自由の相互承認〉が、市民社会の、そして公教育の原理と言えるのかどうかも、絶えず検証し続ける必要があります。『どのような教育が「よい」教育か』では、その理路を克明に描き、そのどこかに誤りがあればこの論は全部崩れますと、全部丸裸にして検証に委ねています。
「信念補強」ではなく「信念検証」。哲学だけでなく、教育実践においてもとても重要なことだと思います。