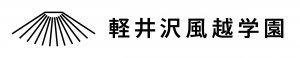『おとうさんの庭』(文:ポール・フライシュマン、訳:藤本朝巳、岩波書店)

2018年2月15日
『おとうさんの庭』
(文:ポール・フライシュマン、訳:藤本朝巳、岩波書店)
(amazon)(楽天ブックス)
「将来の夢は?」という質問に何の気負いもなく心に浮かぶ願いのまま答えられるのは、一体いくつの頃まででしょう。子どもだった自分がなんと答えたか、今となっては思い出せません。
私がこの本に出会ったのは、今から10年ほど前。本城と他数名で「仕事の学校」というワークショップをつくっていた時のことです。金融、メーカー、教員など様々な仕事に就くメンバーでの実行委員会形式で、高校生を対象に「仕事観」について考える5泊6日を長期休みに実施していました。ちょうど「◯◯力」という本が、世の中にたくさん出ていた頃、『力も大事だけど、それよりもその使い方のベースとなる「観」が大事なのでは?』という本城の提案を、よく覚えています。
何の仕事をするかを考える前に、どんなふうに仕事をするかという「仕事観」を育てるため、期間中にいくつかの企業にご協力いただき「仕事観察」の時間をつくりました。「仕事体験」ではなく、いわゆるジョブシャドウと言われる観察の時間です。
この本には、農夫と彼の息子たちがぴったりの仕事に出会っていくプロセスが描かれています。家を巣立つ前の息子に仕事選びを相談された農夫は、家の周りのいけがきを刈り込み、それをじっと見続けるように言うのです。息子が毎日いけがきを観察していると、その枝ぶりがある日、心の奥にあった願いを浮かび上がらせます。思い浮かんだイメージ通りにいけがきを刈り込み、息子たちはその仕事を選ぶ心づもりができるのです。心の奥にある願いを仕事にするって、なんと幸せなことだろうと思います。さて、どうやってそれに出会っていくか。
子どもから大人に近づくにつれ、現実的な進路選択と仕事が紐づいてしまうのは、心よりも頭で見つけようとしている感じがします。文中には、農夫が自分にぴったりの仕事をしているとき、「農夫のこころは、まるで、まきストーブがもえるように、あかあかとかがやきました」と書かれています。
誰かに頼まれたり、急かされたりしているわけでもないのに、自然に身体が動いてやってしまう仕事。他人事でいられない(『自分の仕事をつくる』、西村佳哲、ちくま文庫)仕事をしているときは、確かに、身体の奥で熱量を感じることがあります。
どんな仕事が自分の中で熱量を感じられるのかわからなくなったとき、大人にも仕事観察はおすすめです。あれこれ分析したり判断せずに、フラットな気持ちで観察する。たとえばスーパーのレジで、駅で、保育園や幼稚園、学校で。観て、あるいは仕事ぶりに触れて、私の心が動く時は、私が大事にしたいと思っていることが相手の仕事の中に映し出されるような気がします。
私は教員としての経験はないので、互いに授業見学する機会があることをこれまで知りませんでした。自分の仕事と近ければ近いほど、心が動く場面が多いかも。自分の心が動く肝がわかれば、どんな仕事でも手元で工夫できる余地が生まれるような気もします。
たとえ子どもの頃の願いと違う仕事だったとしても、そうした熱量を感じられる、あるいは熱量を育てていける仕事をみんなができると、子どもたちが大人になって仕事することを楽しみになるような。そんな社会をつくっていくためには、自分自身がまず、農夫たちのように自然と歌を口ずさむようにごきげんに仕事したいものです。
余談その1、自分の子どもに「お父さんの仕事ってなに?」と聞かれた本城の答えは、「本城慎之介」。職業名ではなく、自分であることそのものが仕事、と言いきったエピソードが忘れられません。
余談その2、子どもの頃からの切実な問いが仕事に繋がった苫野一徳の著書、『子どもの頃から哲学者』もどうぞ。

投稿者辰巳 真理子
投稿者辰巳 真理子
変化の大きい立ち上げ期を好み、これまで様々なプロジェクトの事務局に従事。組織は苦手だが、人は好き。おいしいものと日本酒も好き。長年の探究テーマは、聴くことについて。広報、ステークホルダー管理、各種イベント企画・運営などを担当。
詳しいプロフィールをみる